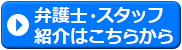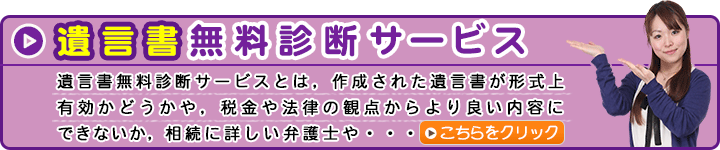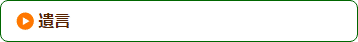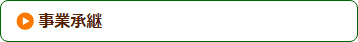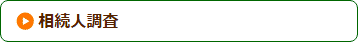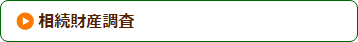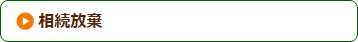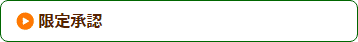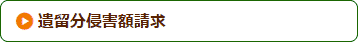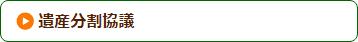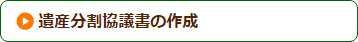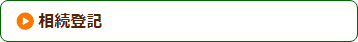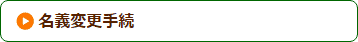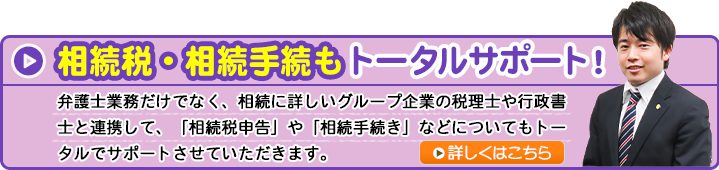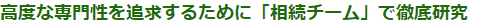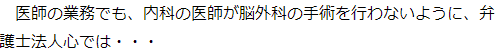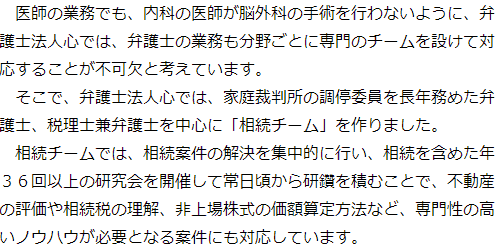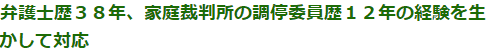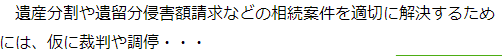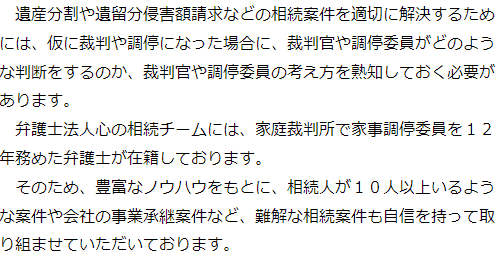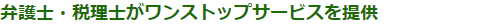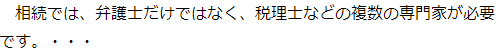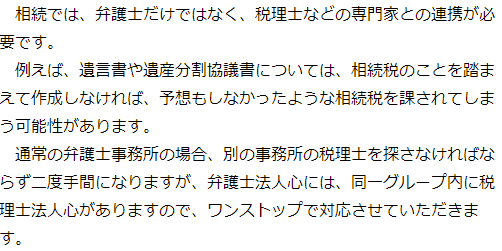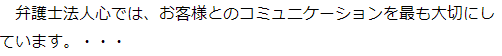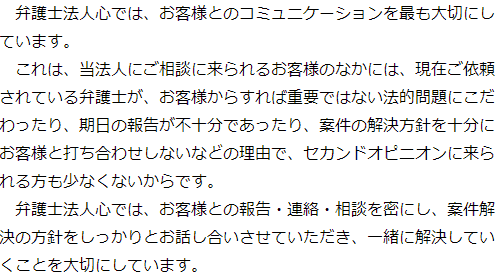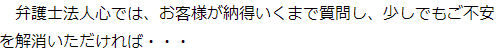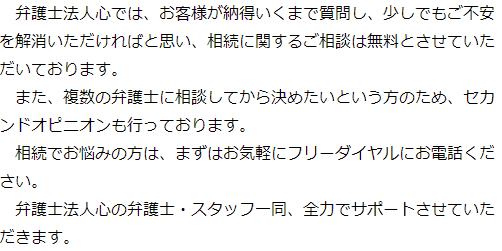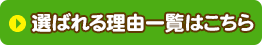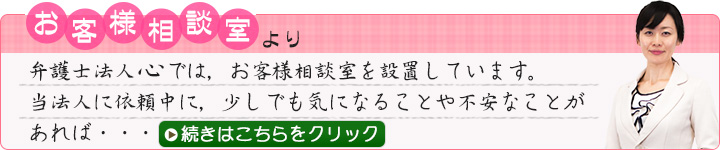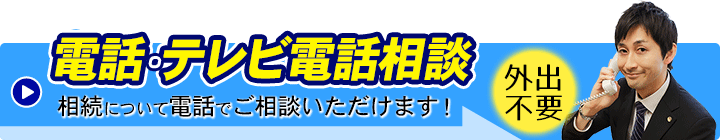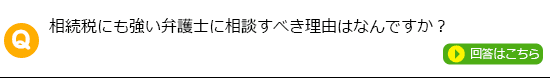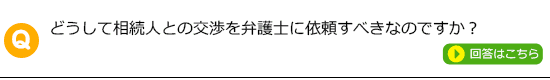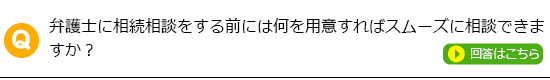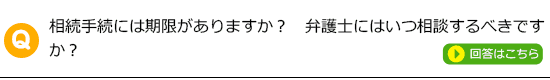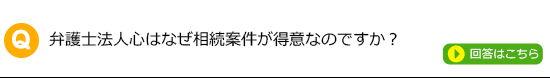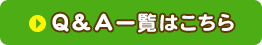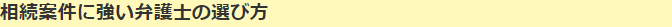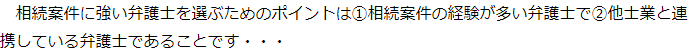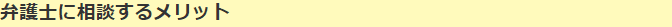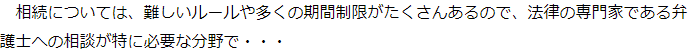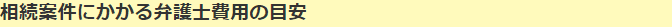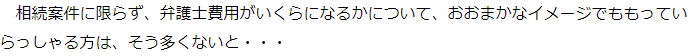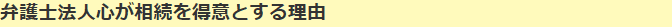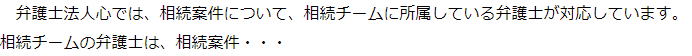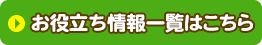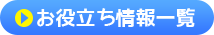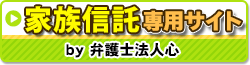サイト内更新情報(Pick up)
2025年6月19日
遺言
遺言の開封について
遺言のうち、公正証書遺言を開封することについては、制限は付されていません。一方、自筆証書遺言および秘密証書遺言を開封することについては、制限があります。封印のある・・・
続きはこちら
2025年4月17日
遺産分割
遺産分割調停にかかる費用
遺産分割調停を申し立てる場合には、申立書に1,200円分の収入印紙を申立書に貼付する必要があります。また、調停を申し立てる際、裁判所から当事者に対して郵便物を送付・・・
続きはこちら
2025年2月20日
相続手続き
相続した家の名義を変更する際の流れ
相続した家の名義を変更する場合、相続登記を行う必要があります。相続登記を行うためには、まず、相続する家を誰が取得するのか決める必要があります。遺言がある場合には・・・
続きはこちら
2024年11月7日
遺留分
遺留分を請求されたらどうすればいいか
遺留分とは、簡単に言うと、相続人に最低限保障された取り分のことです。例えば、被相続人が、「すべての財産を、Aさんに相続させる」という遺言を残していたとします・・・
続きはこちら
2024年10月4日
遺産分割
遺産分割の方法にはどのようなものがありますか?
相続が発生した場合、被相続人の遺産は、一旦は相続人全員の共有となります。そのため、この遺産を、誰に、どのように帰属させるかを確定する必要があります。このための手続きが・・・
続きはこちら
千葉にお住まいの方へ
当法人の事務所は駅から近いところにあり,千葉にお住まいの方にもお越しいただきやすいかと思います。お気軽にご利用ください。
相続を弁護士に相談するタイミング
1 相続について弁護士に相談する場面とは

相続について弁護士に相談するべきタイミングとしては、どの場面においても早ければ早いほどよいといえます。
では、具体的にはどのような出来事があるときに弁護士に相談したらよいか、解説していきたいと思います。
2 遺言を作成するとき
ご自身の相続が発生した後、相続人同士でトラブルが生じることがないように、あらかじめ遺言を作成しようとお考えになる方も多いと思います。
法律上有効と認められる遺言書は、自筆証書遺言か公正証書遺言として作成されることが多いですが、どちらも有効な遺言と認められるためには民法で形式要件が定められており、その形式要件に違反した場合には遺言が無効となってしまいます。
そのような事態が生じることを防ぐために弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば、形式面はもちろん、相続後に発生することが予想されるトラブルも見越して遺言作成のアドバイスをさせて頂くことができます。
3 相続が発生したとき
相続が発生した場合、まず相続人は誰であるのか、相続財産(遺産)として何があるのかを調査する必要があります。
それぞれ調査するためには、それなりの費用と労力がかかりますし、慣れていない方からすると、どこで何を調べるのか見当すら付かないこともあるかと思います。
仮にご自身で調査ができたとしても、万が一相続人や相続財産の範囲に漏れがあった場合、後々相続人間でトラブルが生じることが予想されます。
弁護士に相続人や相続財産の調査を依頼すると、ご自身でそれらの調査をする必要はありませんし、現存する資料から分かる範囲で調査の漏れを防ぐことができるかと思います。
特に遺産の範囲が不明である場合、遺産の数が多い場合には、ご自身の手間と時間の節約のためにも弁護士に相談した方が良いでしょう。
4 遺言が発見されたとき
遺言が発見されたときには、遺言内容が法的に見て有効なものであるのか、遺言を前提としたときにどのような効果が発生するのか等を判断することは難しいかと思います。
また、公正証書遺言以外の遺言が発見された場合、検認という家庭裁判所での手続きをしなければなりませんが、そのような手続きの仕方についても不安を覚える方もいらっしゃるかと思います。
弁護士に相談することで、遺言の有効性、遺言の効力はもちろん、その後の見通しや必要な手続きについても適切なアドバイスを受けることができます。
特に、遺言があるものの、相続人間の仲が良くなく、遺言の有効性や内容の解釈をめぐってトラブルになりそうな場合には、弁護士に相談した方が良いでしょう。
5 遺産分割協議が纏まらないとき
遺産分割協議をしようと思っても、他の相続人と意見の対立が生じてしまい、遺産分割協議が纏まらないケースがあります。
このようなときには、弁護士が代理人として間に入ることで、他の相続人との遺産分割交渉がスムーズに進む場合があります。
また、どうしても任意での交渉が纏まらない場合には、調停や審判といった裁判手続きを行うことがありますが、この時にも弁護士に依頼することで裁判での対応を任せることができます。
また、相続についてのご相談を早めに弁護士にすることによって、トラブルの発生・悪化を未然に防ぎながら、相続手続きを進められる可能性があります。
相続について少しでもお悩みが生じた場合には弁護士に一度ご相談することをおすすめします。
遺言についてお悩みの方
1 遺言書の種類

遺言に関するご相談の中で、「遺言書には複数種類があると聞いたのですが、どのような種類の遺言を作成するべきですか」というご質問を受けることがあります。
一般的によく利用される遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがあります。
自筆証書遺言は、遺言者が自筆で書いた遺言書のことです。
自筆証書遺言が有効となるためには、①遺言の内容となる全文(財産目録を除く)、②日付、③氏名の全てを自筆し、④押印することが求められます。
自筆証書遺言は、公正証書遺言と比較して手軽に作成できる反面、紛失してしまったり、改ざんされてしまったりするリスクがあるため、相続発生後に遺言の有効性が争われるケースも少なくありません。
これに対して、公正証書遺言とは、公証役場の関与の下、遺言者が遺言を作成するものです。
公正証書遺言の場合、遺言書の作成にあたっては、公証人と証人2名が関与します。
公証役場において、遺言者が公証人に対して遺言の内容を伝え、公証人がその内容を筆記したうえで、遺言者と証人にその内容を読み聞かせ、又は閲覧させます。
公正証書遺言は公証役場で作成するため、自筆証書遺言と比較して作成の手続きが煩雑になりますし、公証人に支払う費用も必要になります。
他方で、作成に公証人が関与するため、遺言の有効性等で争いになるリスクを低くすることができます。
2 公正証書遺言作成に必要な資料
公正証書遺言を作成する場合、遺言書案のほかに必要な資料を公証役場に提出する必要があります。
まず、遺産の内容となる預貯金の通帳の写しや不動産の謄本、固定資産税評価証明書の写しが必要となります。
また、遺言者と相続人との関係を把握するため、被相続人と相続人の戸籍謄本の写しも必要となります。
遺贈をする場合には、受贈者の住民票の写しも必要となります。
さらに、公正証書遺言には実印で捺印することになりますので、公正証書遺言作成当日は実印を持参する必要があるほか、当該実印の印鑑証明書も用意する必要があります。
この印鑑証明書は、遺言作成日から遡って3か月以内という有効期限があるため、注意が必要です。
公正証書遺言を作成する場合、上記のような書類が必要となりますし、作成の段取りもやや煩雑となります。
また、公正証書遺言の場合も、遺言書の記載をどのようにするべきか法的な検討が必要になります。
公正証書遺言を作成される場合には、弁護士に一度相談することをおすすめします。
遺産分割について弁護士へ相談をお考えの方へ
1 弁護士に相談するタイミング

遺産分割について弁護士に相談するタイミングは、相続が発生してから早ければ早いほど良いです。
相続が発生した場合、まず相続人は誰であるのか、相続財産(遺産)として何があるのかを調査する必要があります。
しかし、それぞれ調査するためには、それなりの費用と労力がかかりますし、慣れていない方からすると、どこで何を調べるべきなのか見当が付かないこともあるかと思います。
そのため、遺産分割を始めようと思っても、前提となる相続人の範囲や遺産の範囲が確定できず、遺産分割の方針がいつまでも決められないといった事態が想定されます。
遺産分割を円滑に進めるためにも、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
2 相談時にあると良い資料
遺産分割について、弁護士にご相談される際には、相続関係の資料があるとご相談のヒアリングがスムーズになります。
相続関係の書類には、例えば以下のものがあります。
⑴ 相続人関係書類
遺産分割を行うためには、相続人の範囲を確定する必要があります。そのため、被相続人と相続人とのご関係が分かる資料があると、相談がスムーズになります。
戸籍をお持ちの場合には、戸籍をお持ちください。
相続人関係図があると、被相続人と各相続人とのご関係の把握がよりスムーズになります。
⑵ 財産関係資料
遺産分割を行うためには、遺産の範囲も確定する、すなわち、遺産となる財産を洗い出す必要があります。
そのため、遺産分割の御相談の際には、財産に関する資料があると良いです。
預貯金の場合には、通帳や相続開始時点の残高証明書が必要になります。
不動産の場合には、登記簿謄本や固定資産税・都市計画税の課税明細書があると、遺産の不動産を特定することが出来ます。
不動産が収益不動産である場合には、毎月発生する賃料等についても把握が必要になりますので、賃借人との賃貸借契約書があると良いです。
株式等の有価証券がある場合には、証券口座の残高証明書や取引報告書があると、有価証券を把握できます。
不動産に詳しい弁護士に相談した方がよい理由
1 不動産の評価が見通せる
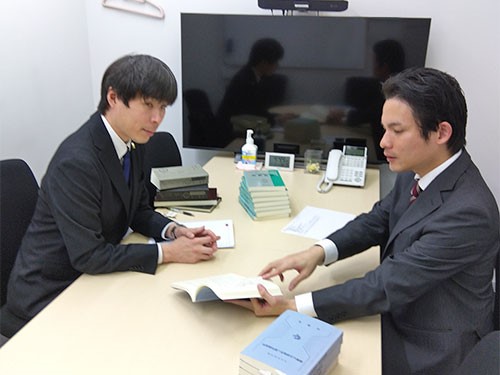
相続関係トラブルにおいては、遺産の中に不動産が含まれている場合に、不動産の評価が争点の1つとなります。
例えば、遺産分割協議において、相続人の一人がその不動産を相続して他の相続人に対して代償金を支払う場合、その相続人としては、できるだけ不動産の評価を低くして、支払うべき代償金の金額を低くしたいと考えるでしょう。
反対に、不動産の相続は希望しないけれども、他の相続人から代償金を取得したいと考える相続人は、不動産の評価を高く見積もって、取得する代償金の金額を高くしたいと考えるでしょう。
このような場合、通常は各相続人が不動産査定書や不動産鑑定評価書を提出し合ったうえで、最終的に不動産の評価を決めることが多いです。
その際、不動産に詳しい弁護士であれば、不動産査定書や不動産鑑定評価書の内容を読み解いたうえで、依頼者の利益になるように不動産の評価の主張をすることが出来ます。
不動産査定書や不動産鑑定評価書が証拠としてある場合、不動産査定書や不動産鑑定評価書で想定されている用途(不動産の最有効使用)や不動産の種類・類型、不動産の評価に付いている条件、採用している取引事例等が適切であるかを吟味することが必要です。
例えば、建物付きの土地を評価する場合でも、その土地を更地としてみるのか、建物の現況利用を前提とするかによって価格は変わり得ます。
その土地に地中埋設物や土壌汚染があるとみるのかによっても、価格は大きく変動します。
このように、不動産査定書や不動産鑑定評価書は、査定価格・評価額の欄だけをみるのではなく、不動産査定書や不動産鑑定評価書の算定の根拠となる計算過程まで読み解くことが大切です。
不動産に詳しい弁護士であれば、不動産関係の資料を読み込んだうえで、不動産の評価に付いての主張を行うことが出来ます。
2 不動産関係トラブルや不動産の売却にも対応することが出来る
相続案件では、不動産関係のトラブルが表面化することがあります。
例えば、遺産である収益不動産の入居者からの賃料が何カ月も未納であり、当該入居者に対して交渉を要するような場合、不動産に詳しい弁護士であれば当該入居者に対しての交渉も行うことができる場合があります。
相続と不動産の対応を一人の弁護士に依頼できるのは大きなメリットです。
また、遺産である不動産を売却する場合、不動産に詳しい弁護士であれば、不動産の売却についても主導して段取りを組むことが出来ます。
どのような条件で売却するのか、売出価格をいくらにするのか、どこの不動産会社に仲介や買取を依頼するべきかも含めて、弁護士に相談できることはお客様のメリットになります。
3 不動産売却のスケジュールの見通しが把握できる
不動産を売却する場合、不動産に強い弁護士であれば、不動産売却のスケジュールを織り込んだうえで、紛争の交渉をすることができます。
例えば、遺産分割事件では代償金の支払いのために、遺留分請求事件では遺留分の支払いのために、不動産を売却しなくてはならない場合があり、相続人間で支払いの期限が決められる場合があります。
また、相続税が発生する場合、納税資金確保のために、相続税の申告・納税の期限までに不動産を売却しなくてはならない場合もあります。
そうすると、弁護士としても、不動産の売却にどれくらい時間を要するかをあらかじめ想定しなければなりません。
不動産に詳しい弁護士であれば、不動産の売却のスケジュールを見通すことができますので、そのうえで交渉業務に臨むことが出来ます。
例えば、土地を売却する場合、買主の購入条件として売主において確定測量することが条件に付いている場合、確定測量のスケジュールも把握する必要があります。
測量を要する場所が、官民境界(道路と対象地との境界)なのか、民民境界(隣地と対象地との境界)なのかによっても、測量のスケジュールが変わってきます。
不動産の決済(不動産が引き渡されて、不動産の売却代金等が支払われる日)までに、測量が間に合わない場合には、買主と協議して決済日を変更する必要も出てきます。
もし、依頼者が不動産の売却代金を相続税の納税に充てようとしていたような場合には、新たに資金調達の算段を立てなければなりません。
不動産に強い弁護士であれば、不動産売買実務に即してスケジュールを立てることが出来ます。
不動産は現金等の流動資産よりも処分に時間がかかり、金額も大きいという特徴があります。
このような特徴があるからこそ、不動産が絡む問題では、不動産の評価や各手続のスケジュールについて精密な見通しを持つことがポイントになってきます。
不動産に詳しい弁護士であればこのような見通しを持つことが出来ますので、不動産が絡む案件でも安心して依頼することが出来るでしょう。